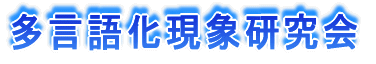
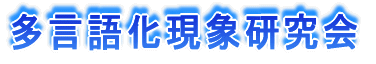
多言語化現象研究会からのおしらせ
運営委員一同
第93回多言語化現象研究会開催のおしらせ
多言語化現象研究会のみなさま
下記の要領で第93回研究会を開催いたします。ふるってご参加ください。 参加方法は末尾をご参照ください。
日時::2025年12月6日(土) 14:00~17:00
場所:大阪大学豊中キャンパス 言語文化A棟2F大会議室
https://www.osaka-u.ac.jp/ja/access/top
豊中キャンパスの②の建物
https://www.osaka-u.ac.jp/ja/access/top
豊中キャンパスの②の建物
*前回と場所が異なりますので、ご注意ください。
対面とオンライン(Zoom)併用を予定:参加申込方法は末尾参照。
無料(どなたでもご参加できます)
第1報告 14:00-15:20
報告者:本田沙也花(大阪大学人文学研究科言語文化学専攻博士前期課)
題目:誰が書いても「やさしい日本語」を目指して――Leichte Spracheの規則を参考に
要旨:「やさしい日本語」は誰にでもわかりやすいことばとして注目され、さまざまな場面での活用が進んでいる。しかし、現状ではその表記や語彙選択の基準が統一されておらず、書き手によって「やさしさ」の度合いが異なる。本発表では現在見られる「やさしい日本語」の表記方法を整理したのち、明確な規則を持つドイツ語のLeichte Spracheを参考に、書き手によらず一定の「やさしさ」を保証できる規則の可能性を検討する。
第2報告 15:40-17:00
報告者:岡本舞夏(関西学院大学大学院言語コミュニケーション文化研究科博士後期課程)
題目:言語態度の初期形成過程を探る
――幼児の異言語に対する社会的選好を手がかりに
要旨:多様な言語や話者と関わることが日常化される現代社会において、言語態度研究の重要性は一層高まっている。人々の言語に対する態度は幼い頃から形成され始め、話者への評価や感情、また言語行動そのものに現れるようになる。本発表では、認定こども園で実施した調査結果を基に、就学前幼児の母語以外の言語に対する態度を左右する要因について検討する。さらに、これらの考察を踏まえ、言語態度の初期形成過程を捉える視点と、今後の幼児を対象とした言語態度研究の可能性について模索する。
●申込み:
〇オンライン参加の場合:前日までに以下にアクセスし、事前登録をお願いします。登録後、ミーティング参加に関する情報の確認メールが届きます。
https://us02web.zoom.us/meeting/register/m2HEheD1QFyXyrFWs6sCXw
登録者には当日参加用リンク(本人のみ有効)が送付されます。これで事前登録が完了します。資料は当日配布します。
〇会場に直接お越しの場合:webmaster@tagengoka.sakura.ne.jp 宛に、名前・所属と、懇親会参加有無を明記のうえ、送信してください。懇親会会場の予約、資料準備などの必要があるので、お早めにお申込みください。
主催:多言語化現象研究会 https://tagengoka.sakura.ne.jp/
多言語化現象研究会事務局:webmaster@tagengoka.sakura.ne.jp
研究会の趣旨 研究会の組織・運営、連絡先 関連研究会リンク
関連・新着図書
「今そこにある多言語なニッポン」(くろしお出版 2020年)
「事典 日本の多言語社会」(岩波書店 2005年)
「まちかど多言語表示調査報告書」 (2006年)
「ことばと社会 11号 特集:移民と言語①」(三元社 2008年)
「日本の言語景観」(三元社 2009年)
「ことばと社会 12号 特集:移民と言語②」(三元社 2010年)
「多言語社会日本ーその現状と課題」(三元社 2013年)
(「教師用手引き」三元社HPで公開しました)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
多言語化現象研究会事務局:webmaster☆tagengoka.sakura.ne.jp(☆を@でおきかえてください)
研究会ホームページ: http://tagengoka.sakura.ne.jp